

| 別府 と周辺 2010 |


 


|
|
( 別府へ ) ・長い間お世話になった別府の定宿が、近く閉鎖するとの話を聞き、2010年4月中旬、急遽別府へ出かけることにした。 初めて別府へ行ったのは、1969年(昭和44年)の4月末だったと思う。その前年から広島勤務になっていたので、広島から国道2号線を徳山まで行き、周防灘フェリーで国東半島北端の竹田津へ上陸、今の国道213号を通って別府に入った。当時の213号は国道とはいえ、舗装も余りされていない悪路であった。このときは、二日目に「やまなみハイウェイ」を通って、阿蘇を往復した。霧の中を突っ走り、坂道の頂上近くになると道がなくなってしまうようで、怖かったのを覚えている。草千里や中岳の火口をはじめて見た。あれから別府へ何回行ったのか、正確には思い出せない。 ・最初行ったときから15年後に福岡勤務になり、このときは単身赴任だったので、別府へしばしば出かけて、休暇を過ごした。別府まではバスで行くのだが、高速道路は、大宰府から甘木までしか開通していなかったと思う。それ以外は一般国道を行くことから、5時間近くかかったように記憶している。ただ、筑紫平野や筑後川沿い、日田の町や天ヶ瀬温泉などを通ったりで、バス旅行の風情は楽しめた。今は福岡天神から別府北浜まで、2時間余である。 また、別府を起点として、国東半島や臼杵などへ出かけた。11月の連休だったと思うが、国東半島一周の定期観光バスに乗ったことがある。当時は今と違って、バス会社にも余裕があったのであろう、A、B、Cの3コースが用意されていた。そのうちCコースという、余りポピュラーでないところも回るコースを選んだためか、大型バスに客は私と愛媛の高校の先生という人との2名だった。見学先の寺院の方とガイドさんは、顔馴染みなことから、座敷に通され炬燵にあたりながら、蜜柑をすすめられ歓談するという、普通の観光バスでは味わえないような体験もさせてもらった。 ・福岡勤務を終えてから20年以上が過ぎたが、この間も別府を訪れる機会が多かった。最近は湯布院へよく出かけるが、観光客で賑わう中心部から離れた鳥越地区のギャラリーや高級オーディオ装置でクラシックが聴けるカフェなどが印象深い。前回は2006年3月で、また行きたいと思いつつ、結局4年ぶりになってしまった。今後は九州へ行くことがあっても、今までのようにあえて別府へ行く、ということにはならないかもしれない。 |
| 国東、杵築、日出~別府 |
|
第1日目 ・行きは8時過ぎの便にしたが、日曜日だったためか、大変空いていた。多分消席率は、5割以下だったのではないか(機材はA320)。 ( 国東 ) ・10時過ぎに大分空港着。空港から別府方面は何度も通ったが、最初来たとき以来行ったことがない北部の国東方面へドライヴすることにした。同宿の友人が16時過ぎに別府入りするので、それまでに別府へ戻ることを前提に、許す限り国道213号を北上することとする。現在の日本では、どこへ行っても道路はきれいに整備されているが、ここも同様である。41年前の記憶はないが、所々に廃止された旧道やトンネルを見ることができた。あそこを通ったとはとても信じられないような道幅の狭さ、そしてトンネルはクルマ1台がやっと通れるようなところもあった。今は国東市になっているが、旧町名でいうと、空港のある安岐から、武蔵、国東を通り半島最先端の国見へ入る。 ・国見の中心部の少し手前にある「国見ふるさと展示館」に寄る。 この展示館は、明治初年に築造された庄屋邸を保存・利用し、国見町の歴史や文化が分かるように展示しているもの。内容は、① 国東半島全体を特徴づける、「六郷満山」と呼ばれる8世紀ごろから創建された寺院群による仏教文化についての紹介、② 国見出身で「日本のマルコ・ポーロ」ともいわれるペトロ・岐部という神父 の足跡をたどる展示、③ 国見出身の芸術家の作品、④ 民俗文化の展示、から構成されている。また、大変趣のある美しい庭園も一見の価値がある。 ・このうち、②以下がこの町固有のものである。ペトロ岐部(1587~1639)は、キリシタン禁制下に日本を出て、インドから単独でアラビアの砂漠など、陸路をエルサレム経由ローマまで行ったという、驚くべき人物である。ローマで神父になり、禁教下の日本へ帰り殉教の道を選んだ。人間業を超えた強靭な肉体と精神力を備えていたと思われるが、彼をこのような行動に突き動かした要因としては、篤い信仰の他、彼が水軍の子孫であったことと、そもそも鎖国以前の日本は貿易、人間両面でアジア中心にかなり海外展開を行っていた、すなわち海洋国家の道を歩んでいたということが背景にあるように考えられる。隣接の城山公園には、記念聖堂と大きな銅像が建てられている。また、公園出入り口横には赤いつつじの植込みに囲まれて、聖人に次ぐ"福者"に列せられたことを記念した、真っ白なマリア像が建てられている。 |
| (写真はクリックで拡大します。) | ||||
 |
 |
 |
||
| 国見ふるさと展示館 | 庭園 | 庭園 |
|
・国見出身の芸術家としては、江藤哲画伯(1909~1991)の作品が印象に残った。号数はよく分からないが、波しぶきのあがる海を描いた大きな油絵は、重厚で圧倒する迫力があった。 民俗文化の分野では、農機具や食器を始めとする生活用品などが多数展示されている。手回しのタイガー計算機まで置いてあった。昭和40年代初頭まで使われていた計算機だが、その頃は庄屋さんではなく、町の有力者として、何か計算する仕事をしていたのだろうか。 ここで12時を過ぎてしまい、先の行程を考えて213号を戻ることにした。 |
 |
 |
 |
||
| 2階ギャラリー入口 | 江藤画伯の作品(撮影許可済み) | 城山公園入口のマリア像 |
| ▲ページのトップへ |
|
( 杵築 ) ・今回は、いつも通過するばかりで寄ったことのない、杵築の町と日出城跡を見て別府に入る計画だ。大分空港を通り過ぎ、空港自動車道に入らず、213号で杵築へ向かう。 まず、杵築城。13世紀末に大友氏一族「木付氏」の城として築造されたのが始まりで、大友氏が滅亡し、江戸時代になり、松平氏が藩主になったが、将軍家からの朱印文に誤って「杵築」と書かれたのを契機に、それまでの木付から杵築と呼ぶようになったという。現在の「城」は、昭和45年に本丸の跡に建てられた、三層の「模擬天守閣」であるが、出入り口がアルミドアで出来ていることからも分かるように、実体は城の形をした資料館である。とはいえ、海に面した小高い山の上に建てられており、遠くからは要害堅固という言葉を想起させる、杵築のシンボルとなっていることは間違いない。 この山全体が、城山公園としてよく整備されている。公園の中には、この地方の代表的な石造文化財170基を集めた一角があり、国東の仏教文化の一端を窺うことができる。 |
 |
 |
 |
||
| 杵築城 | 杵築城からの展望 | 城山公園のフジ |
 |
 |
 |
||
| 石造物群 | 国東塔 | 宝篋印塔 |
 |
 |
|
| 城山公園・青筵神社の八重桜 | 同ツツジ |
| ・次いで城山公園を降り、武家屋敷などが江戸時代の風情をよく残しているいう、城下の町並みを訪れた。城山の西側に南北二つの台地があり、それぞれの台地に武家屋敷が、台地に挟まれた谷間に商人の町が位置するという配置になっている。武家屋敷は、かなり良く保存されていると感じたが、全体を回ると相当の時間を要することが分かり、メインと目される北台武家屋敷しか見ることができなかったのが残念だった。ゆっくりと時間をかけて、散策する価値のあるところだ。 |
 |
 |
 |
||
| 勘定場の坂(北台への上り口) | 同左・頂上付近 | 勘定場の坂の土塀 |
 |
 |
 |
||
| 藩校の門 | 大原邸(家老屋敷) | 土塀 |
 |
 |
|
| 酢屋の坂 | 商人の町 |
| ▲ページのトップへ |
|
( 日出城址 ) ・日出には日本画で有数のコレクションを擁する「二階堂美術館」があり、前回訪れた。 何事につけ東京など大都市中心の発想が多いなかで、小さな町にこのような優れた美術館があるのは嬉しいことである。 もっとも、それ以外は日出といえば「城下カレイ」しか念頭になかったのは事実であり、せめてその「城」とはどのような所かを見ておきたいと思ったのである。 国道213号から10号に合流し、暘谷(ようこく)駅入口の信号を入るのだが、杵築のように遠くから城が見えるわけでもなく、分かり易いところではない。関が原の戦いの後、木下氏が別府湾に面した日出の台地に築造したのが「暘谷城」であるが、明治になって廃城となり、現在は日出小学校になっている。石垣とお堀の跡が残されているだけであるが、石垣から海岸までの一帯を「城下公園」として整備している。学校前には、日出町観光協会の新しい案内所が開業準備中で、担当の婦人から、丁寧な解説を頂いた。なお、城址の前に滝廉太郎の銅像がある。廉太郎は竹田出身と思っていたが、滝家は代々日出藩の家老職にあり、自身日出出身と称していたそうである。 公園下の海には、何箇所か清水が湧いており、その付近に生息するマコガレイが「天下の美味・城下カレイ」というわけである。昔から、希少な魚であったが、近年特に少なくなっており、値段も高くなっているようである。大分空港の売店でも、最近ブランド化に力を入れている「姫島カレイ」ばかりが目についた。 |
 |
 |
 |
||
| 暘谷城址碑(日出小学校入口) | 石垣(城下公園) | 同左 |
 |
 |
 |
||
| お堀跡 | 暘谷城復元図 | 城下公園遊歩道 |
 |
 |
 |
||
| 遊歩道から別府方面を望む | 城下公園からの展望 | 藩校致道館 |
| ▲ページのトップへ |
| 昭和の町、宇佐、湯布院 |
|
第2日目 ・生憎小雨模様の中、9時半出発。10号線を北上し、日出の街中を抜けると「ハーモニーランド」の看板が見えた。他の多くのテーマパーク同様、経営に厳しいものがあったことは想像に難くないが、経営主体の変更があったものの、継続されているようで、敬意を表したい。 立石峠を右折して山道を豊後高田の「昭和の町」へ向かう。 ( 昭和の町 ) ・昭和30年代の町を再現した豊後高田の「昭和の町」は、いわゆる「レトロテーマパーク」のひとつで、地方の小都市における町おこしの成功例である。 昭和30年代をテーマにしたテーマパークは、1996年にオープンした東京池袋のサンシャインシティ内「ナムコナンジャタウン」が嚆矢ではないかと思う(現在は餃子自慢商店街)。その後、2002年に東京臨海副都心のデックス東京ビーチに「台場一丁目商店街」がオープンし、いずれも話題になった。そのほかにも、各地に相当数のレトロテーマパークがあるようだ。 ・テーマパークのみならず、映画などでも昨今昭和30年代ものが流行っている。あの時期社会人になった人達や、子どもだった年代がリタイアし、昔を懐かしむということであろうが、今のように豊かではないものの、日本全体が目標を持ち、上昇志向に燃えていた、活気のある時代だったからこそ、懐かしいのではないか。バブル経済に熱狂したり、翻弄されて自分を見失ったことへの反省もあろうが、より基本的には、30年代以降の高度成長の過程で、東京、大阪などへ人口が集中するなどして社会構造に大きな変化があったにも拘らず、新しい連帯感のある社会になっていないことが背景にあるような気がする。 ・「昭和の町」は、2001年から着手され、2006年頃から広く知られるなったらしい。合併前の旧市内の人口が2万人足らずのところ、20万人を超える来街者があるという。それまでは商店街は寂れる一方で、建物の7割以上が昭和30年以前に建てられたものというから、およそ外から人が来るような街ではなかったはずであるが、その寂れきったところを逆に売り物にしたわけである。既存商店街の他に、新たに「昭和ロマン蔵」という室内型誘客施設を設置しているが、これも古い倉庫を利用したもので、極めて軽装備である。従って、投下資本は僅少で、他のテーマパークのように資金面から破綻する心配もないといえよう。 |
| (写真はクリックで拡大します。) | ||||
 |
 |
 | ||
| 商店街の風景(駅通り) | 商店街の小路風景(新町) | ボンネットバス |
 |
 |
||
| 昭和ロマン蔵入口 | ロマン蔵・電飾 |
 |
 |
 | ||
| ロマン蔵・電飾 | 食堂 | 煙草屋 |
 |
 |
 | ||
| 駄菓子屋夢の博物館 | 駄菓子屋 | 同左店頭 |
| ▲ページのトップへ |
|
( 宇佐 ) ・国道213号を10分程度で、宇佐八幡宮に着く。前回は、2005年3月だったので5年ぶりだが、それ以前に来たときの紅葉が綺麗だったのが一番印象に残っている。パソコンの扱いの手違いで多くの写真が消えてしまったが、ここの写真も残っていないのが残念である。 表参道から鳥居を入ったすぐ左に蒸気機関車が展示されているが、以前からあったのかどうか、記憶にない。全体が真新しい雰囲気なので、最近のことかもしれない。1891年ドイツ製で、元は国鉄所有であったが、大分交通に譲渡され、昭和23年から宇佐参宮線(神社前~日豊本線宇佐駅~豊後高田)で昭和40年に廃止されるまで使われていたそうだ。 ・宇佐八幡近くの宇佐風土の丘にある「大分県歴史博物館」を見学しようとしたが、本日は休館日ということで、建物外観だけで引き返した。 宇佐別府道路の宇佐入口手前に「鷹栖観音」の標識があり、寄ることにした。小さなクルマ一台がやっと通れるような、川岸の道を行くのだが、ガードレールなどもちろん無いし、手掘りで岩をくり貫いたような狭いトンネルを通らなければならず、一寸怖かった。この観音堂は、奈良時代に造られたもので、後背部を岩山の中腹にもたせ掛け、前面を長い柱で支える「懸造り」と呼ばれる建築様式によっている。平安時代作の木彫りの像が安置されている。後で調べたら、川の対岸の県道沿いの観音寺の奥の院であり、観音寺から橋を渡って来るのが通常かつ安全なルートらしいことが分かった。無事離れることが出来、安堵した次第。 |
 |
 |
 |
||
| 神橋 | 西大門 | 本殿(二之御殿) |
 |
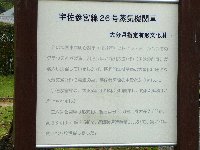 |
 |
||
| 宇佐参宮線26号機関車 | 同左説明板 | 大分県立歴史博物館 |
 |
 |
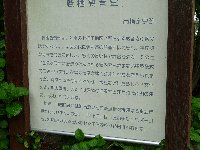 |
||
| 鷹栖観音堂 | 同左 | 鷹栖観音堂説明板 |
| ▲ページのトップへ |
|
( 湯布院 ) ・宇佐から湯布院へは、宇佐別府自動車道・速見ICから大分自動車道へ入り、湯布院ICまで30分強と想定していたが、安心院を過ぎる辺りから霧がかかり始め、速見、日出付近は濃霧で右側の黄色いラインを頼りに運転する他ないような状態になった。湯布院方面は一貫して右車線を走ればよいのは幸いだった。車線変更はとても危険な状態だったと思う。一旦追突事故が起きたら、数十台の玉突き事故になった可能性もあり、鷹栖観音に続いてヒヤヒヤが続いた。この区間は、濃霧で有名らしく、我々が通った後、翌日まで通行止めになったそうだ。結果、国道10号は大変な渋滞となった。 ・湯布院は本格的な雨になった。湯布院で雨になったのは初めてである。狭い湯の坪街道に入り、旅館「玉の湯」の売店「由布院市」で「柚子こしょう」を求める。関東の人には馴染みがないかもしれないが、柚子こしょうは風味が良く、大抵の料理に合う優れものである。数ある中で、玉の湯のものが最も質が良いように思い、愛用している。湯布院へ寄ったときは必ず買って帰ることにしている。次に、別の店で柚子茶を買う。柚子茶もいろいろあるが、ここの「ゆずっ子」に決めている。以前は別府市内や福岡でも求めることができたが、現在はここだけである。 ・湯の坪街道は、狭い通りに観光客相手の店が並ぶ、人通りが多いところで、鎌倉の小町通りのような感じもあるが、全体がゆったりとした雰囲気・風情が感じられる湯布院の中で余り違和感を感じない。いずれにしても、雨で由布岳も見えないどころか、写真撮影すら儘ならない状態だ。 この近くで休憩するとしたら、玉の湯の「ニコルズバー」が、静かで、空気の良い林の中でコーヒーを飲む感じで気に入っているが、中心部から離れた鳥越地区へ行くこととする。 |
 |
 |
 |
||
| 玉の湯庭園 | GALLERY無量塔・鄭東珠作品室 | 珈琲HAMANO |
|
・まず、「GALLERY無量塔」へ。玉の湯と並ぶ
湯布院最高級旅館の一つ「山荘無量塔(むらた)」のオウナーが、画家・書家の鄭東珠氏を招いて開設したギャラリーであり、「チョントンジュ作品室」と称されている。4年前に伺ったとき、鮮烈な印象を持ったので、今回も是非寄ろうと思っていた。平面的な絵画ではなく、和紙に数十回重ね塗りをするとか、キャンバスに石膏を塗って立体感のある作品にするといった手法で、特に鮮やかな深みのあるブルーには感動させられる。また、墨象画は素人目にも躍動感のある素晴しいものと思う。 お茶は、「無量塔」の"Tan's bar"か、"HAMANO"かと迷った挙句、前回も寄ったHAMANOにした。アットホームな雰囲気と、あの凄いオーディオ装置で何か聴かせてもらおうと思ったのがその理由である。評判のチーズケーキも頂いてみたかった(評判どおり美味しかった)。喫茶スペースから、オーディオルームに置かれたグレングールドのレコードが眼に入ったので、このレコードでバッハを聴かせて頂き、満足して帰途についた。 |
  |
| 「別府と周辺の情報」へ |

 |
「別府と周辺 2010」BGM:滝廉太郎「花」 |