



 「2010夏の沖縄」はこちら
「2010夏の沖縄」はこちら
 
 
 「2010夏の沖縄」はこちら 「2010夏の沖縄」はこちら
|
| 2010 読谷の史跡・戦跡など |
|
2010年の沖縄旅行の2日目午前、恩納村南隣の読谷村へ出かけた。2007年に訪問できなかった世界遺産のうち、座喜味城跡がこの地にあることから、この機会を利用して訪れることとした。併せて読谷には沖縄戦の戦跡の他、豊富な史跡・名所があることから、そのいくつかをも訪れた。 ( 座喜味城跡 ) ・時間の制約と、極力涼しいうちに回りたいとの考えから、6:30に朝食を摂り、直ちに出かけた。58号線の喜名交差点の場所に沖縄戦まで村役場(番所)が置かれていた関係であろう、読谷村入口のような感じで石碑が立っている。ここから入り、7時15分頃には座喜味城跡入口に到着。 |
| (写真はクリックで拡大します。) | ||||
 |
 |
 |
||
| 読谷村国道58号線から・ 向こう側は嘉手納弾薬庫地区 | 喜名交差点の読谷村入口碑 | 世界遺産を示す碑 |
|
・座喜味城は、15世紀前半に、琉球王国第一尚氏(中山)第2代尚巴志の命により恩名村出身の按司護佐丸が築城したもの。その後護佐丸は、東海岸の勝連城を牽制する役割を与えられ、中城に移り、同城も完成させたことから、築城の名手とも言われている。因みに、護佐丸は、勝連城主阿麻和利の謀略とされている乱により自害した。その後阿麻和利は、首里王府を攻め込もうとしたが滅ぼされ、何故か読谷村に墓がある。護佐丸は中城に立派な亀甲墓があるようだ。両者とも不明の部分もあるらしいが、いずれも琉球王国の基礎がなお不安定な時代における、有力豪族(武人)である。 ・この城は、手前の二の郭と一段高い一の郭から構成されている。標高120m、城域面積約4,000㎡で、沖縄のグスクとしては中規模のものである。 入口から階段を上り、琉球松の林の中のごく緩やかな坂道を抜けると、二の郭入口のアーチ型石造門が見えてくる。アーチ部分がかみ合う部分にクサビが打ち込んであるが、この形式が沖縄に現存する石門の最も古い形を現しているそうだ。 |
 |
 |
 |
||
| 城跡入口 | 入口階段上からの琉球松の林の道 | 二の郭石造門を望む |
 |
 |
 |
||
| 二の郭の城壁外側 | 二の郭石造門 | 二の郭石造門・アーチ繋ぎ目の楔 |
| ・二の郭の広場の先に階段があり、一の郭へ入る門が見える。一の郭広場は広大で、城主の住んだ建物跡や灯籠がある。城壁の上に上がると壁が厚いことが分かる。城壁のカーブが美しい。展望は大変良く、旧陸軍の高射砲陣地になっていた要害の地であることも頷けるが、沖縄戦では艦砲射撃で相当やられたに違いない。戦後は米軍のレーダー基地になっていたが、1972年の本土復帰直後から復興が始まり、まもなく返還された由。 |
 |
 |
 | ||
| 二の郭石造門・内側 | 二の郭広場、一の郭石造門を望む | 一の郭石造門 |
 |
 |
 | ||
| 一の郭内部の広場 | 同左 | 一の郭広場の建物跡 |
 |
 |
 | ||
| 灯籠 | 一の郭城壁上から | 同左 |
|
・城壁の外側に遊歩道もあり、この一帯が公園として極めて綺麗に整備されている。遊歩道の途中に月桃の実がなっていた。秋になると赤くなるはずだ。 駐車場の横に村立民俗資料館があるが、この時間はまだ開いていない。城跡入口の近くに、高倉(穀物倉庫)とサーターグルマ(砂糖車、砂糖絞り機)が展示してあった。 |
 |
 |
 | ||
| 月桃の実 | 高倉 | サーターグルマ |
| 座喜味城跡を後にし、一旦58号線に戻り、大湾から西海岸の嘉手納町との境界に近い渡具知ビーチへ向かう。 ( 読谷の戦跡と渡具知ビーチ ) ・沖縄戦において、米軍は1945年3月26日に慶良間列島へ上陸したが、本島へは4月1日に読谷へ上陸したのが最初である。何故読谷に上陸したかというと、読谷には、旧日本陸軍の「北飛行場」が、そしてすぐ南東の嘉手納に「中飛行場」があり、まずこの二つの軍事要衝を押さえるという目的があったに違いない。そのような意味で、読谷は6月まで続いた沖縄本島における地上戦の端緒となった場所として、その後の米軍支配を経て、現在なお大きな問題を抱えている現代沖縄に至る原点のひとつとも称し得る場所なのである。 ・米軍の規模は、艦船1,400〜1,500隻、兵員183千人という圧倒的なものであり、また、日本軍は後方へ撤退していたことから、米軍は無抵抗の中易々と上陸した。そして、この日のうちに両飛行場を占領し、翌2日には恩納村と東海岸の石川の線で沖縄本島を分断、本島の制圧に向かったのである。 そのような事情から、読谷村には戦跡が大変多い。村のホームページでは、33ヶ所の戦跡が紹介されている(末尾資料1)。 ・渡具知ビーチは、遠浅の美しい海岸である。このビーチを中心とする南北10kmに及ぶ海岸沖に大量の艦船が現れ、上陸してきたのである。現在は、一帯が泊城公園として整備され、地元の方の憩いの場となっている。観光客は見かけない。 公園内の海沿いの崖の上に米軍上陸碑が建てられている。上っていく途中「ハブに注意」という看板が見えたが、雑草は綺麗に刈り取られており、安全を確保しているよう窺えた。 渡具知ビーチの北側に木綿原ビーチがあり、「木綿原遺跡」がある。2千年以上前の沖縄貝塚時代の遺跡で、1977年の発掘で7基の箱式石墓と17体の化石人骨や土器を出土した。箱式の石墓の出土は九州の弥生文化の習俗が南下して来たことを示しているとされている。 このビーチの先は米軍基地(トリイステーション)で、立ち入り禁止である。 |
 |
 |
 | ||
| 満潮からやや引き始めた 渡具知ビーチ | 同左 | 米軍上陸碑とパーゴラ |
 |
 |
 | ||
| 米軍上陸碑 | 同左 | 同左 |
 |
 |
 | ||
| 木綿原遺跡 | 木綿原ビーチ、左奥が渡具知ビーチ | ハマヒルガオ |
| ( チビチリガマへ ) ・県道6号をトリイステーションの前を通り、チビチリガマへ向かう。県道から外れるが、赤瓦のトイレの前ということで分かり易かった。地上レベルからかなり下りた窪地の一角に口を空けている壕がチビチリガマである。 米軍上陸時、高齢者、女性、子ども中心の残された村民の混乱は想像に余りある状況だったに違いない。 この洞窟こそ、そのような中で、4月2日肉親相互が殺しあうという凄惨な集団自決が行われた場所である。避難者約140人中83人が非業の死を遂げたが、その6割が18歳以下の子どもで、米兵に殺される位なら、まず自分で愛するわが子を殺してから自決したという。壕の前に立つと、生存した方の生々しい証言などが頭に浮かび、なにか身体全体がすくむ思いというか、現場に行かなければ分からない、なんとも名状し難い気持ちで、祈らずにはいられない。なお、今でも遺骨が残されていることから、壕の奥には立ち入り禁止である。また、入口前には、1987年4月彫刻家金城実の指導により平和の像が建設されたが、同年8月に破壊されるなど、遺族の方にとっては耐え難い事件が起きたこともある(現在の像は1995年に再建されたもの)。 丁度2人連れの女性を案内されているご婦人の説明を、暫く一緒に伺わせて頂いた。近くで「まーみなー」というペンションを経営する傍ら、戦跡などを案内される他、ソプラノ歌手としても活躍されている会沢さんという方だった。 チビチリガマと対照的に、ハワイからの帰省者が、米軍が住民を殺すことはない旨の説得を行い、1千人もの人が投降し、助かったという壕がシムクガマである。 末尾資料4は、最近発見された米軍カメラマン撮影によるフィルムに関するレポートであるが、上陸直後の読谷村の様子が写されている。 |
 |
 |
 | ||
| チビチリガマ | 同左・入口の立ち入り禁止の看板 | 遺族会の石碑 (碑文:末尾参照) |
 |
 |
 | ||
| 平和の像 | 同左 | 壕の周辺 |
| ( 読谷村役場 ) ・読谷村は占領直後において、村域の実に95%が米軍に押さえられ、'72年の本土復帰時でも73%を米軍基地が占めていた。その後、幾多の返還運動により米軍施設の返還が進んだものの、現在なお37%は米軍施設が占めている。その大部分は極東最大の弾薬庫と言われる「嘉手納弾薬庫」である。すなわち、国道58号の東側地域の全て、北隣の恩納村の手前からは、国道を挟む両側が弾薬庫地域である。林に覆われ気がつかないものの、弾薬庫の中を通る形なのである(ページ冒頭の写真参照)。このような重要な弾薬庫に核兵器がないのは寧ろ不自然だという見方もあるようで、そうだとすれば、マリンレジャーや美ら海水族館に向かうクルマ、観光バスは核兵器の近くを何も知らずに通っているのかもしれないということになるが、実態は神のみぞ知るということか。 ・沖縄の市町村の中でも際立って米軍基地のウェイトが高い読谷村において、基地以外の部分だけで街づくりを行うということは、事実上困難だったことは想像に難くない。そのため、読谷における街づくりは、必然的に基地の返還を実現しつつ行わざるを得ないという困難なものとなったのである。「やちむんの里」や基地の中に建設を実現させた国体会場の運動広場、そして村役場などはその例である。 すなわち、将来返還されるべきものとの考え方から、基地返還を前提にした長期的・計画的な土地利用計画を策定することとし、米海兵隊読谷補助飛行場という米軍基地を共同利用する、という戦略的な手法により、基地内部に1987年の国体会場を作ることに成功し、1997年には現在の村役場を建設したのである(正式返還は2006年)。並大抵の努力ではなしえない偉業であることは間違いない。役場の周辺を歩くと平和への強い希求が伝わってくるようであるが、戦後の村民の方々のご苦労を考えれば、納得がいく。 |
 |
 |
 | ||
| 読谷村役場 | 三代目読谷村役場の碑 | 憲法9条の碑 |
 |
 |
 | ||
| 読谷村役場門柱 | 同左 | 滑走路跡の道路 |
| ( やちむんの里、喜名番所観光案内所 ) ・帰りに「やちむんの里」で、前回見なかった「北窯」を見た。読谷山窯より大きく、沖縄最大の規模という。前回寄ったお店に顔を出したら、覚えていて頂いたのには驚いた。予想もしていなかっただけに、凄く嬉しかった。 次いで、「喜名番所観光案内所」に寄った。戦前まで読谷村役場のあったところに建てられている観光案内機能のみの道の駅である。1853年6月、ペリー率いる艦隊が浦賀へ来る前に琉球に寄った際、ここで休憩したとされている。その様子を描いた絵の写真があった。 以上で午前中という時間の制約下ながら、今回の読谷村訪問を終えた。 |
 |
 |
 | ||
| 北窯 | やちむんの里にて | 同左 |
 |
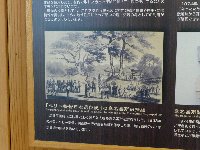 |
 | ||
| 喜名番所観光案内所 | 喜名のペリー一行図(ハイネ画) | 戦前の喜名番所付近の図 |
| なお、読谷村に近い恩納村仲泊に、沖縄で最も古いとされる3,500年前の住居跡である「仲泊遺跡」がある。近世まで行われていた風葬の墓跡や、王府時代の石畳の街道(国頭方西道)跡なども含め、史跡として整備されている。また、近くには護佐丸の座喜味移転前の山田城跡がある。1609年の薩摩侵攻の際の古戦場でもある。ホテルからクルマで5分位のところなので、5日目の朝訪れてみたが、鬱蒼とした道を登る必要があるようなので、隣接する村立博物館の人に聞くと、最近ハブが出たという。単独行は危険と考え、引き返した。ガイドをして貰える機会があれば、見たいものだ。 |
 |
 |
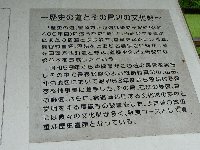 | ||
| 仲泊遺跡碑 | 国頭方西道碑 | 周辺文化財の解説 |
 |
 |
 | ||
| 恩納村博物館 | オキナワキョウチクトウ (別名ミフクラギ、駐車場にて) | 同左の実(毒がある) |
|
[参考資料] 1 読谷村ホームページ : 「バーチャル平和資料館」、「読谷村の戦跡めぐり」 2 大田 昌秀 「写真記録 これが沖縄戦だ」(琉球新報社、1983改訂版) 3 大田 昌秀 「沖縄戦とは何か」(久米書房、1985) 4 NHK ETV特集「よみがえる戦場の記憶〜発見 600本の沖縄戦フィルム〜」(2010.6/27放映) (注) 碑文は以下のとおりです。 チビチリガマから世界へ平和の祈りを 1945年4月1日、米軍はこの読谷村の西海岸から沖縄本島へ上陸した。それは、住民を巻き込んだ悲惨な沖縄戦・地上戦であった。その日のうちに、米兵はチビチリガマ一帯に迫っていた。翌2日、チビチリガマへ避難していた住民約140名中、83名が「集団自決」をした。尊い命を喪った。 あれから38年後、やっと真相が明らかになった。その結果、83名のうち約6割が18歳以下の子供たちであった。その他、2名が米兵の手によって犠牲になった。 「集団自決」とは、「国家のために命を捧げよ」「生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪過の汚名を残すことなかれ。」といった皇民化教育、軍国主義教育による強制された死のことである。 遺族は、チビチリガマから世界へ平和の祈りを、と「チビチリガマ世代を結ぶ平和の像」を彫刻家金城實氏と住民の協力のもとに制作した。しかし、像の完成から7ヵ月後、11月8日、心なき者らにより像は無残にも破壊された。住民は怒り、遺族は嘆いた。 全国の平和を願う人々はそのことを憤り、励ましと多大なカンパを寄せた。あれから七年余が経過し、平和の像の再建が実現した。チビチリガマの犠牲者への追悼と平和を愛するすべての人々の思いを込め、沖縄戦終結50周年にあたり、ふたたび国家の名において戦争への道を歩まさないことを決意し、ここにこの碑を建立する。 1995年4月2日 チビチリガマ遺族会 |
  |
| 沖縄の観光案内・史跡等へのリンク |

 |